【薬剤師が選ぶ】新人薬剤師にオススメの勉強本まとめ25選|2025年版
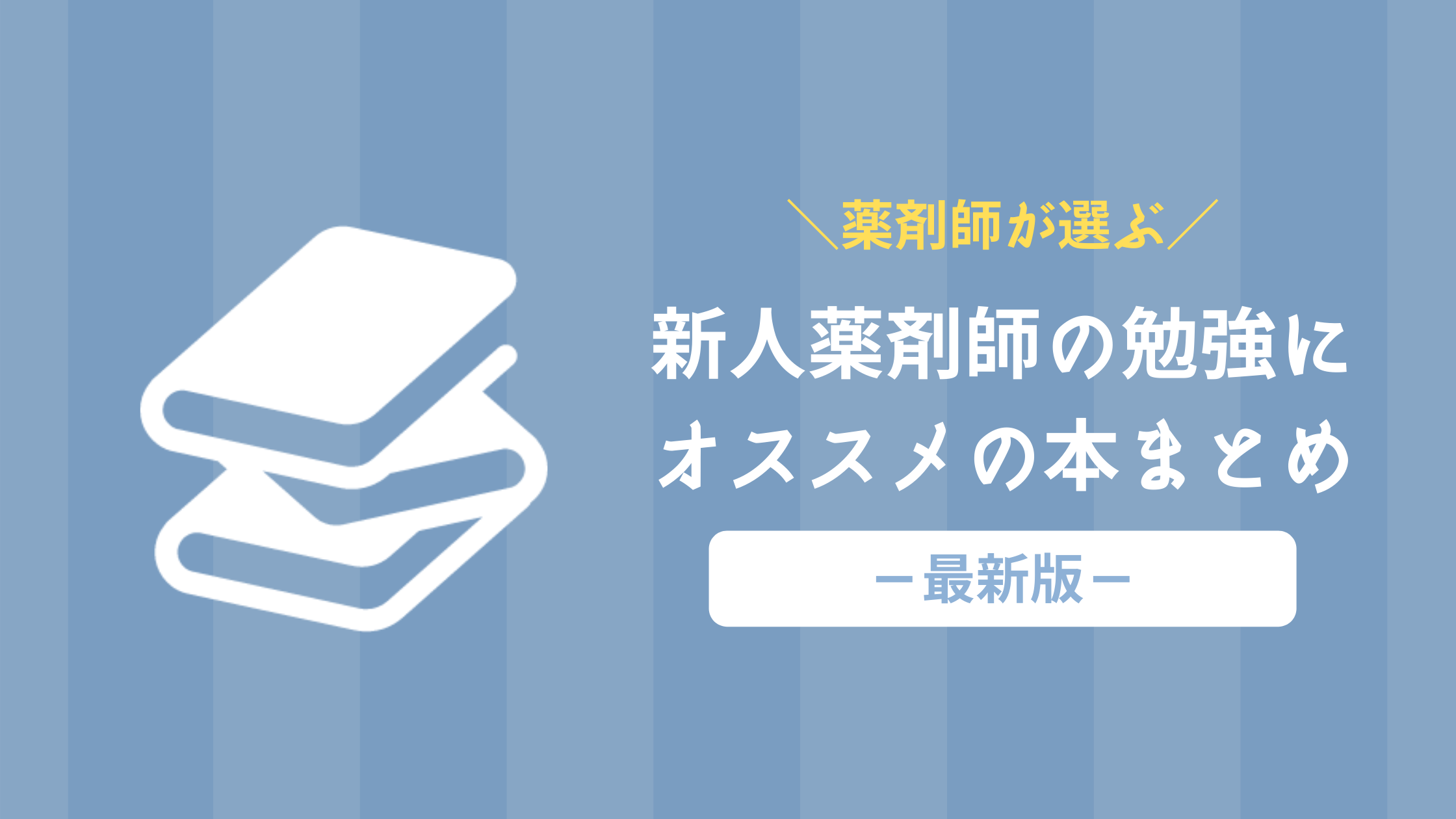
アフィリエイト広告を利用しています
新人薬剤師におすすめの勉強本ってなにがあるんだろう・・・
この記事はこういった悩みを持つ新人薬剤師向けの記事です。
- 新人薬剤師におすすめの勉強本まとめ
- 勉強本をお得に買う方法を紹介
どーも、病院薬剤師のひゃくさん(@103yakulog)です!

薬剤師国家試験を見事合格し薬剤師になったわけですが、薬剤師になってからも勉強はずっと続きます。
勉強の方法は色々ありますが、多くの薬剤師は本を読んで勉強しているでしょう。
今回、この記事では実際に僕が読んできた本の中から新人薬剤師にオススメの本を紹介したいと思います。
もちろん新人でない薬剤師さんにもおすすめの本ばかりです!
また、「抗菌薬を学びたい!」「精神科の薬を学びたい!」などの目的別のおすすめの本も紹介しています。
目次からあなたが勉強したい項目を探してみてください!それぞれの本でおすすめポイントを書いているので参考にしてみてくださいね。
この記事で紹介する本で勉強して、どんどん成長していきましょう!
転職を考えている新人薬剤師は、「1年目の新人薬剤師が転職で失敗しないためにやるべきこと」をチェックしてみてください。
1年目の転職で失敗する理由と失敗しないための方法を分かりやすく解説しています。
新人薬剤師におすすめの勉強本
薬がみえる
- 薬について網羅されている
- イラストが豊富で理解しやすい
- 病態についても学ぶことができる
「薬がみえる」は本のタイトルのように、病態と薬物治療を分野ごとにまとめてあるため、薬がどのように臨床で使われているか調べることができます。
処方を見て分からないことを調べたり、普段の勉強に用いたり、いろんな用途で使える新人薬剤師の勉強に必須のアイテムと言えるでしょう。
全てカラーで構成されており、イラストも多く、医師や看護師も絶賛の新人薬剤師にオススメのシリーズです。
2020年4月28日に待望の「薬がみえる vol.4」が出版されました。
「薬力学」、「薬物動態学」、「相互作用」、「製剤学」、「薬剤の使用と実務」など、薬剤師に必要不可欠な知識まとめられているので、是非チェックしてみてください。
自分の興味のある分野がまとめてある1冊だけ買うのもありだね!

処方がわかる医療薬理学
- 1冊に薬の要点がまとめてある
- 作用機序から薬の使い方まで網羅されている
- 2年で更新されるので新しい情報で構成されている
先ほど紹介した「薬がみえる」はとても詳しく書かれてある一方で、分野ごとに3冊に分かれていたり、なかなか改訂されず最新の情報が載っていなかったりというデメリットがあります。
この「処方がわかる医療薬理学」は、1冊に様々な病態をまとめたものになっており、2年に1度新しいものが出版されているため最新の情報を学ぶことができます。
また、薬剤ごとにどのような違いがあるのか、どのように使い分けがされているのかもまとめてあるので、新人薬剤師が医師の処方意図を把握するためにも重宝される1冊です。
そこまで分厚くなく持ち運びにも便利なので重宝しています!

薬の比較と使い分け100
- 類似薬の違いが分かりやすくまとめてある
- 医師の処方意図がより理解できるようになる
- こぼれ話が面白い
同じACE阻害薬の違いや、同じHMG-CoAの違いなどの個々の薬を比較した上で、何が違うのか、どのように使い分けすればいいのかを学ぶことのできる1冊です。
この本を読むことで、処方を見た時にどうしてこの薬が選ばれているのか、処方意図を理解することができるようになります。
さらに、こっちの薬の方が良いのではないかという提案も医師にできるようになるかもしれません。
本の下部に書かれてある「こぼれ話」も面白く、薬剤師のスタートに読んでおくことで他のみんなと差を付けられること間違いなしの一冊です。
僕が最初に買った本が「薬の比較と使い分け100」で、それがきっかけで薬学の本を読む楽しさを知りました!

薬局で使える実践薬学
- 薬の疑問を会話形式でわかりやすく解説してくれる
- 薬学的思考を高めることができる
「半減期24時間の睡眠薬は飲むと1日中眠くなるのか?」や「CCrとeGFRの使い分けは?」などの薬剤師の日常業務での疑問を、理論立ててわかりやすく解説している本になっています。
実践薬学を読むことで、この本に書いてある知識を得られるだけでなく、自分で理論立てて考える力が身に付くでしょう。
なにより薬学部で学んだ薬物動態学などを用いて話が進んでいくので、薬学部での知識を無駄にすることなく成長に繋げることができます。
新人薬剤師にもとてもおすすめの1冊ですが、全薬剤師におすすめできる本といえるでしょう。
現役薬剤師からも非常に人気の本で、僕もこの本から多くのことを学ばせていただきました!

医薬品情報のひきだし
- 添付文書やインタビューフォーム、論文等に基づいて薬についての疑問が詳しく解説されている
- イラスト付きでポイントが簡潔にまとめてある
- 医薬品情報をどのように実践に活かせるかがわかる
薬剤師国家試験では基本的に教科書的なことを学びますが、実際に現場に出てみると教科書的な知識だけでは解決できないこともたくさん出てきます。
この「医薬品情報のひきだし」では、薬剤師業務中に出てくる疑問を添付文書や論文を基にしっかりと解説してくれているので、「なぜ」なのか「どうすれば」いいのかなどが理解できます。
また、論文とか難しいなぁと思っている新人薬剤師も、イラスト付きで簡潔にまとめてあるのでとても理解しやすい本となっています。
PPIで下痢になる理由は?とかステロイド経口剤の換算は?とかいろんな疑問を解決できますよ!

薬剤師レジデントマニュアル
- 薬剤師に役立つ情報が1冊のポケットサイズにまとめられている
- ガイドラインなどの要点がまとめられている
薬剤師レジデントマニュアルは日常業務でよく触れる疾患が1冊のポケットサイズにまとめられた本です。
総論では調剤、DI、高齢者、検査、薬剤管理指導の要点を簡潔に記載し、各論は感染症、糖尿病、高血圧など主要54疾患が解説されています。
ポケットサイズなので薬がみえるほどの情報量はありませんが、各ガイドラインのポイントや疾患の要点などがまとめられており、気になることを業務中にさっと確認することに適した本といえるでしょう。
家などでの勉強には適していませんが、現場で働く新人薬剤師が白衣のポケットに入れておきたい1冊です。
小さな本ですが、非常に多くの情報がまとめられているので新人薬剤師の時は重宝していました!

【目的別】薬剤師におすすめの勉強本
しくじりから学びたい薬剤師向け
しくじり処方提案
新人薬剤師のしくじり処方提案をもとに、指導薬剤師が改善点をめちゃくちゃわかりやすく解説してくれるというストーリー仕立ての本。
だれもがやってしまいそうな処方提案がたくさん登場し、なぜだめなのか、どうすればよかったのかを根拠をもとに解説してくれているので、とても記憶に残りやすい一冊です。
抗菌薬を学びたい
抗菌薬の考え方、使い方
医師向けに書かれてある本ですが、抗菌薬がどのように選択せれているのか、どんなことに注意が必要なのかなど、薬剤師にもわかりやすい内容となっています。
タイトルの通り抗菌薬の考え方や使い方が学べるので、抗菌薬の勉強をしたい薬剤師にもってこいの一冊です。
感染症プラチナマニュアル
ポケットサイズの小さな本ですが、抗菌薬の解説や各感染症の解説がしっかりまとまった一冊です。
抗菌薬からのアプローチ、微生物からのアプローチ、疾患からのアプローチなどの章に分かれており、さまざまな視点から抗菌薬を学ぶことができる点がおすすめです。
白衣のポケットに入るので、抗菌薬および各感染症について調べたい時にすぐ取り出せるのがメリットですね。
精神科薬を学びたい
薬剤師のための精神科の薬
教科書的な内容や添付文書の内容を学ぶだけでは精神科の薬って理解できないですよね。
この本では実際に医師がどのような意図で精神科の薬を処方しているのか、薬剤師としてどのようなことに注意すべきか、症例を解読していくことで学べるようになっています。
5分野(大うつ病性障害、双極性障害、神経性障害、統合失調症、認知症)についてわかりやすくまとめてあるので、新人薬剤師だけでなくすべての薬剤師にお勧めの一冊ですね。
緩和治療薬を学びたい
緩和治療薬の考え方、使い方
この本は教科書で学ぶような内容に加え、実臨床ではどのように薬剤を選択していけばいいのか語り口調でわかりやすく書かれています。
痛み、吐き気、食欲不振、呼吸困難、消化管閉塞、便秘、倦怠感、眠気、不眠、不安、抑うつ、せん妄などなどの緩和治療で使う薬が幅広く網羅されており、緩和治療の勉強をしたい薬剤師にとてもおすすめの1冊です。
緩和治療薬は薬剤師が力を発揮しやすい領域の一つだと思うので、一度読んでみるといいでしょう。
輸液を学びたい
レジデントのためのこれだけ輸液
輸液と一言で言っても、生理食塩液や5%ブドウ糖液などそれぞれにしっかりと特徴があり、薬剤師は理解しておく必要があります。
輸液を学びたい薬剤師におすすめしたいこの本は、研修医向けに書かれた本ですが薬剤師にもとってもわかりやすく書かれてあります。
それぞれの輸液の特徴、体内のどこに分布するのか、どんな時に使うのか、どんなことに注意すべきか、輸液の基本的なことはこの1冊で十分にまとめられているので、輸液の勉強したいと思っている薬剤師はこの本を読んでみるといいでしょう。
ICU・救急の薬を学びたい
病棟・ICU・ERで使える クリティカルケア薬
クリティカルケアで処方される頻用薬の使い方・押さえておくべきポイントを豊富なエビデンスに基づき網羅された1冊。
薬効別に薬がまとめてあり、それぞれの薬がどんな使い方をするのか、どのような違いがあるのか、どのようなことに注意すべきなのかが非常にわかりやすく書かれてあります。
また、投与量、調整法、投与法、配合変化まで載っており、病院で働く薬剤師にかなりおすすめの本です。
ICU/CCUの薬の考え方、使い方
ICUやCCUで使われるような鎮痛薬、鎮静薬、循環作動薬、降圧薬などなど、他の本ではあまり詳しくまとめられていないような、だけど病院薬剤師として知っておきたい内容がびっしりまとめてある本です。
ノルアドレナリンやドブタミンの使い方、使い分け、注意点をあまり理解できていない病院薬剤師も多いと思います。
実際僕もその一人でしたが、この本を読むことで使い分けを理解でき一気に成長できたように感じていますね。
少し値段は高いですが、それだけの価値がある1冊だと思っています。
OTCを学びたい
OTC医薬品の比較と使い分け
「薬の比較と使い分け100」の著者の児島悠史先生が書かれており、図解が多くとてもわかりやすくまとめてあります。
患者さんの症状やニーズに合ったOTCの選び方について、有効成分の特徴を徹底比較し、約800点の参考文献を明記して解説されており、妊婦・授乳婦への対応など、現場で役立つ117ものQ&Aがまとめられているので、薬剤師として働くなら読んでおきたい1冊ですね。
実際にOTCを扱わない病院薬剤師でも患者さんから相談を受けることがあるので、OTCの知識を付けたい場合におすすめです。
相互作用を学びたい
これからの薬物相互作用マネジメント(PISCS)
薬の相互作用をみるときに添付文書に掲載されている相互作用を確認すると思いますが、すべての薬剤に対しての検証が行われているわけではないので実際は情報が不十分である場合があります。
薬物相互作用の強さと予測を臨床的なリスク評価設定に応用するためのフレームワークがPISCS(ピスクス、Pharmacokinetic Drug Interaction Significance Classification System)です。
この本ではPISCSが詳しく解説されており、添付文書に載っていない情報でも予測することで薬物治療に活かすことができます。
PISCSを正しく身に着けることができれば、薬剤師としてより現場で活躍できるようになるでしょう。
検査値を学びたい
薬剤師のための基礎からの検査値の読み方
薬剤師国家試験ではなんとなく覚えていた検査値も、現場では非常に大事な情報の一つになります。
病態の推測や、副作用が起きていないかモニタリングする時も検査値の推移を追ったりしますからね。
この「薬剤師のための基礎からの検査値の読み方」では、それぞれの検査値がどのようなものを反映しているのか、推測される病態はどのようなものか、また患者さんに説明する際に気を付けることなどが非常にわかりやすく書かれてあります。
また、検査値の説明だけでなく症例解析トレーニングという章もあり、どのように検査値を使って読み解けばいいのか分かりやすく解説されているので、新人薬剤師におすすめの一冊です。
副作用を学びたい
副作用を診るロジック
この本は総合診療医により書かれた本で、実際の現場で薬剤性の副作用をどのように鑑別しているか、その思考過程が詳しくわかりやすく解説されています。
医師の思考過程がわかれば薬剤師として副作用を考えるポイントがわかりますし、副作用が疑われる場合に医師にどのような情報提供をすればいいのかポイントを押さえることができます。
実際に副作用が疑われた場合にどのように考えればいいのか、その思考能力を高められる1冊です。
3ステップで推論する副作用のみかた・考え方
薬剤師として働きだすと「あれ?副作用かも?」と思うような場面に遭遇することがあります。
そんな時に、本当に副作用なのか、また副作用であった場合どのような対応をすべきなのかの判断を迫られます。
この本では、副作用を疑った時にどのような対応をすればいいのか、症例を用いて学ぶことができます。
薬剤師は薬のスペシャリストとして、薬物治療だけでなく副作用の面でもしっかり対応できるようになるべきなので新人薬剤師の勉強におすすめの1冊です。
薬歴のつけ方を学びたい
誰も教えてくれなかった実践薬歴
薬歴を書くことは薬剤師業務の中でもとても重要なものになっていますが、薬歴を上手くつけることができているか、上手く活用できているかは個々の薬剤師によって大きく変わってきます。
この本では薬歴のつけ方を始め、薬歴を通してどのような薬学管理をしていけばいいのか実践的な考え方を身に付けることができます。
単に薬歴の書き方を学べるだけでなく、薬学を活用するツールとして患者さんにどうかかわっていくか学ぶことができるので、新人薬剤師のうちに身に付けておくと更なるスキルアップが期待できるはずです。
医療情報の見つけ方・読み方を学びたい
薬剤師のための医療情報検索テクニック
本当に欲しい情報を正しく集めるためには、添付文書やインタビューフォーム、診療ガイドラインなどの医療情報を検索するテクニックが必要になってきます。
この本では、新人薬剤師にもわかりやすく情報収集の方法についてまとめてあり、さらにその情報がどれほどの信頼性があるのか、その情報をどのように活用すればいいのかというのを対話形式で教えてくれます。
また、論文の検索テクニックもこの本で学ぶことができるので、薬剤師としてのスキルが一気に上がること間違いなしです。
1日1論文、30日で、薬剤師としてレベルアップ!
薬剤師が現場でよく見る薬や話題についての医学論文をピックアップし、それを読んだ複数の薬剤師の考え方がまとめられた本です。
論文の読み方だけでなく、それをどのように活かせることができるのか、薬剤師の意見がまとめてあるのでとても勉強になります。
また、同じ論文を読んでも、薬剤師によって似た見解や異なる見解などが出てきて、より多角的に論文を読む力が身につくはずです。
論文を読んでない薬剤師も、まずはこの本から読んでみると論文を読むハードルが下がるはずです。
医学を学びたい
医師ともっと話せるようになるための基本的臨床医学知識
薬剤師になって痛感するのは薬の知識だけでは薬剤師の力は十分に発揮できないということです。
薬剤師として活躍するには基本的な各疾患の知識を身につける必要があります。
この本は現場でよく見る疾患について、薬剤師が医師と話すために必要な基本的な医学知識が存分にまとめてあります。
この本を読むことでより医師に情報提供しやすくなるでしょうし、医師の処方意図も理解しやすくなるはずです。
モダトレ(画像診断 × 薬物治療)
この本では難しい理論なしですぐに使えるモダリティ(医用画像機器)の知識と薬物治療に活かすポイントがわかりやすく解説されています。
日本病院薬剤師会の会長も「本書を繰り返し読みながら臨床現場での経験を積み重ねていくことで、薬剤師の業務に深みが増すことは間違いない」と絶賛している本です。
「モダトレ」を読むことでカルテの記載内容がより理解でき、医師の治療方針などもより把握できるようになるでしょう。
新人薬剤師におすすめ!勉強本をお得に買う方法
薬剤師向けの本って高いな・・・

Amazonプライムでお得に買う
書籍は中古品以外は定価以下で売られることが無いので、お得に買うためにはポイント還元を上手く利用する必要があります。
そこで僕がお得に買うために入会しているのが、「Amazonプライム」です。
公式サイト:Amazonプライム
- ポイント還元率が高い
- 送料無料
- 1ヶ月無料体験期間あり
- プライムビデオやプライムミュージックなど他のサービスも充実
AmazonプライムとはAmazonが提供している有料会員サービスで、特典の種類がとても多いのが特徴です。
料金は年間プランと月額プランがあり、年間プランだと年間4,900円(税込み)です。
月額あたりに換算すると408円になりますね。
月額プランは月額500円(税込み)なので、年間プランより92円高くなっています。
Amazonプライム会員であれば、本を買う時に通常より多くのポイント還元を受けることができます。
時期によって還元率は変わりますが、最大15%の還元を行っていることもあるので必見ですね。
さらに、送料無料で利用できるので、かなりお得に買うことができます。
また、本とは関係ありませんがプライムビデオやプライムミュージックなども利用できるので、とてもお得なサービスだと言えるでしょう。
気になる人は、初回1ヶ月無料で体験できるので、試してみることをおすすめします。
僕が本を買うのは基本的にAmazonプライムです。
年会費はかかりますが、送料無料で早く届くし、プライムビデオなどのコンテンツを利用できるのでオススメです!

公式サイト:Amazonプライム
新人薬剤師におすすめの勉強本まとめ
今回は新人薬剤師にオススメの勉強本について紹介しました。
この本以外にもたくさん良い本があるので、これらの本をきっかけに色々な本を読んでみるといいかと思います。




























